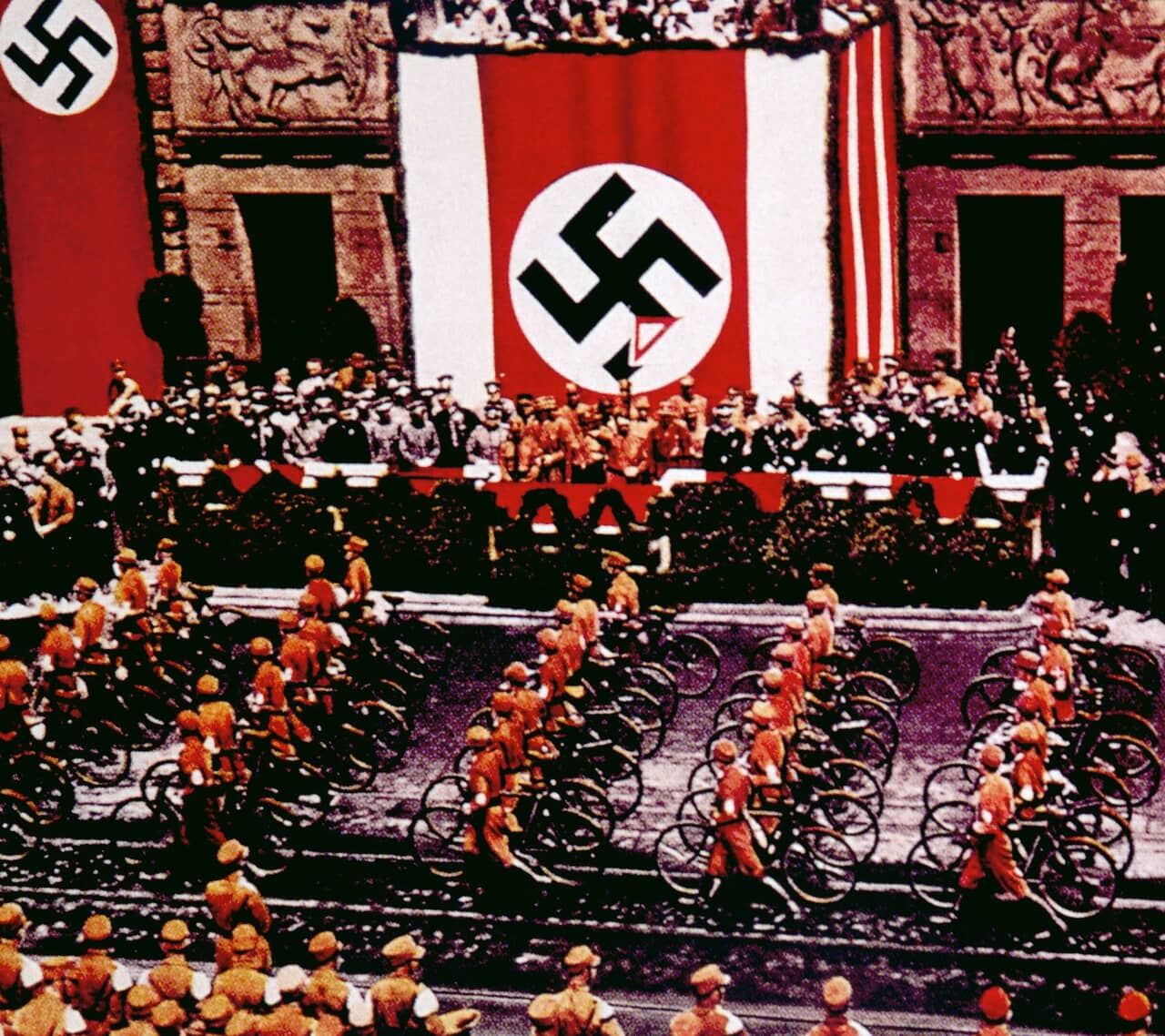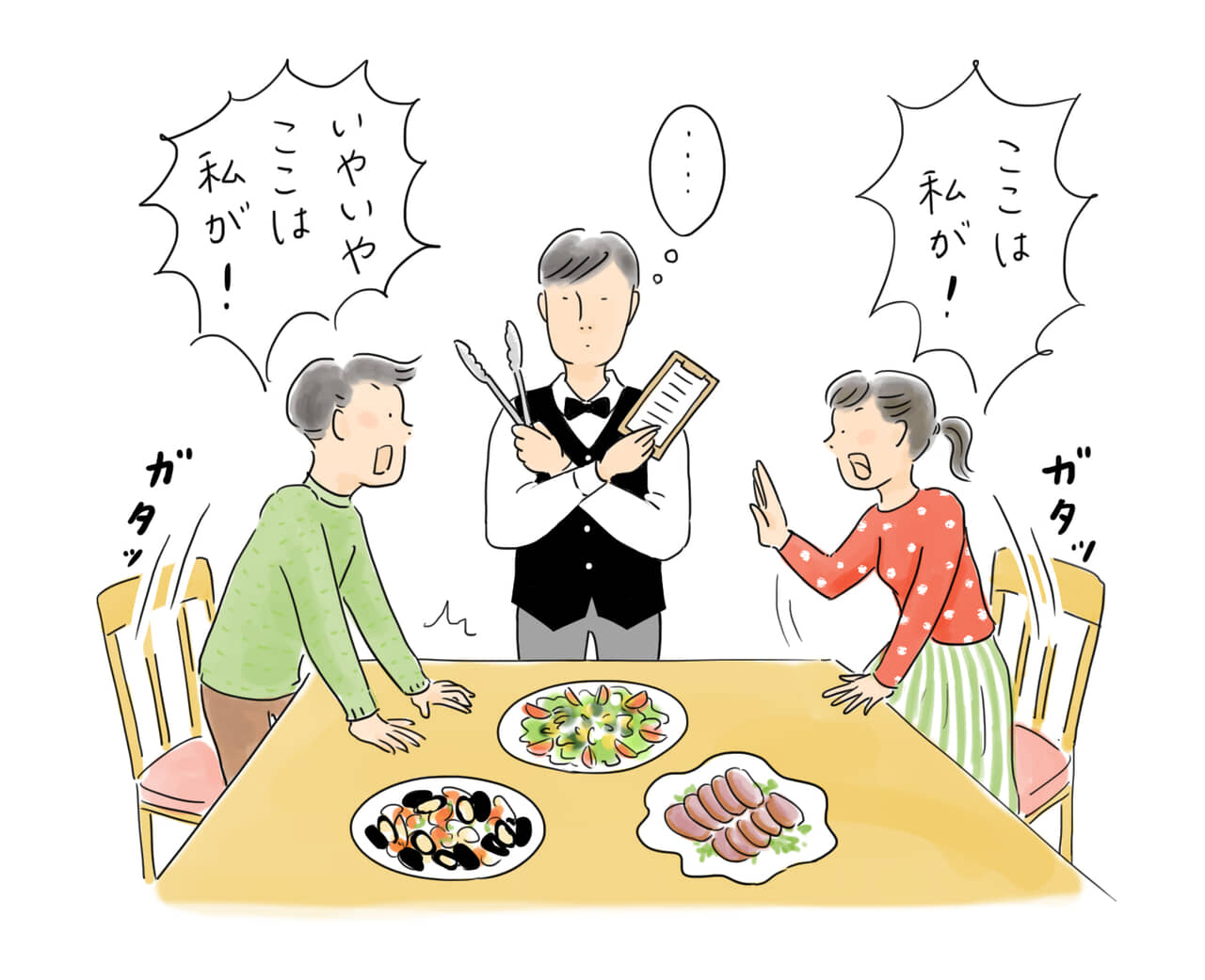「若さを失うことは、可能性を失うことか」 雨宮まみ『40歳がくる!』葛藤を強さにして生きた証【若林良】
雨宮の場合はどうか。住本も参加した鼎談「令和に読む雨宮まみ こじらせ・性・消費」(『中央公論』2024年1月号)では、ライターの藤谷千明は『女子をこじらせて』における、「好きな人とキスできる人生とできない人生だったらどっちがいいか、それを考えたらたとえどんなに傷つくことが待っていようと、私は何度でも、キスできる人生を選びます」という言葉に共感を示しつつ、しかし現代では、そもそもキスをしたくない人の存在を考慮する必要性についても語る。あるいは、『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)における、「独身というだけで世の中はなんと生きづらいのでしょう」という本の全体を貫くような慨嘆。結婚に変わるオルタナティブな関係性が浸透してくるような未来では、後世にはより伝わりづらい(共感を得づらい)言葉となりうるかもしれない。
時間がたち、世間の価値観が変遷、あるいは洗練されることによってわかることはあるし、同時に、個人の感覚としても認識が変わることもある。いわゆるフェミニズムの文脈における、もしくはより広範に、思想史における雨宮の位置づけが今後どのように変わるか。その方面に疎い私には予想こそつかないし、雨宮の著作は、後世からは否定されるものとなるのかもしれない。
「後世からは否定されるものとなるのかもしれない」……。いや、正直に言えば、私自身はまったくそのように思っていない。そんな断言を支えてくれるのは、本書の巻末に収録された「AVライター失格」という、“雨宮の原点とも言えるエッセイ”である。2007年に発表されたこのエッセイにおいて、雨宮はAV監督であった恋人への愛憎と、自身の奥底にあった醜い感情との対峙を、思わずのけぞるような熱意で語り続ける。
「自由になりたい。自由になりたい。劣等感から、自分のみにくさから、彼に執着することから、ギャルを見るたびに胸が痛むことから。自分を、うまく愛せないことから。ぜんぶ捨てて、あたらしい気持ちで、朝の光を浴び、うれしいときに笑い、かなしいときに泣き、好きな人に好きと言い、嫌いなものからぱっと離れ、気分のままの服を着て、気分のままに歌をうたったり、歩いたり、はしったり、そんなことをしていたい」
近年市場の縮小が続き、若い世代からは縁遠いものになってきているAVの世界だが、ここであらわになる、のちのすべての著作に通底する雨宮の自身への真摯さに、心を撃たれるものが誰もいない社会などありうるだろうか。その場を乗り切るためだけの打算や処世術だけが幅を利かせ、真摯な問いが無視される社会なんて、糞食らえでしかない。
感情が原稿のなかでいろいろと沸騰してしまい恐縮だが、沸騰ついでに、最後に自分自身の話をもう一つ。私は40歳になる7年後に、もう一度この本を読み直してみようと思う。30代前半の私にもここまで刺さる内容となっているのだから、40歳で再読をした際には、自身の「伴走者」としての雨宮をさらに実感でき、恐らくは低迷期を迎えている、自分の大きな起爆剤となるに違いないと思うからである。
追記:なお、危うく下げたままで終わるところだったが、本稿を書くにあたり『東京を生きる』も9年ぶりに再読した。本書もまた、あらためて読むと大きな満足感を……といった形で終わらせたいところだが、本書における雨宮の「東京」への渇望ぶりには、正直なところ、そんな微温的な表現では済まされない恐ろしさを感じた。雨宮の「東京」への想いは、関東出身・在住の私にはまだまだ自分の想いとしては咀嚼できないものがある。『東京を生きる』をどのように受け止めるか、『40歳がくる!』の再読も含めた、今後の自分の課題としたい。
ただ、それでも、『東京を生きる』におけるいくつもの表現に、現在の私が打たれたことも付言しておきたい。とくに、「六本木の女」という章で、森瑶子を評した「美しい服は、装身具は、みじめさから女を救う。哀しみや不幸、憂鬱ですら、ある種の美しさに変えてくれる。彼女には、その魔法が使えたのだ」という言葉は、ちょうど「服」を「文章」に置き換えれば、雨宮自身を表した言葉のようにも、雨宮自身がなりたかった自分を投影した言葉のようにも感じ、思わず涙が出てきた。
文:若林良